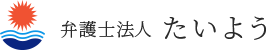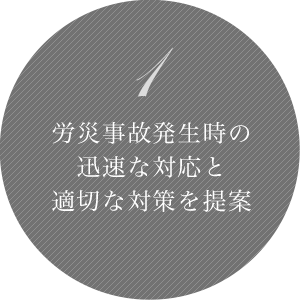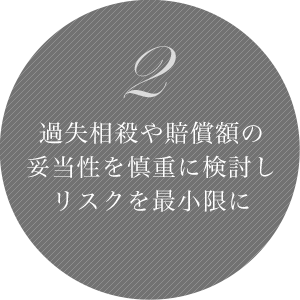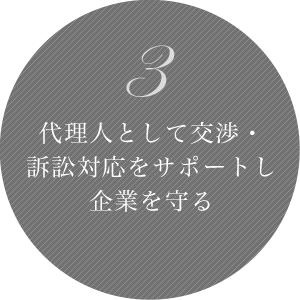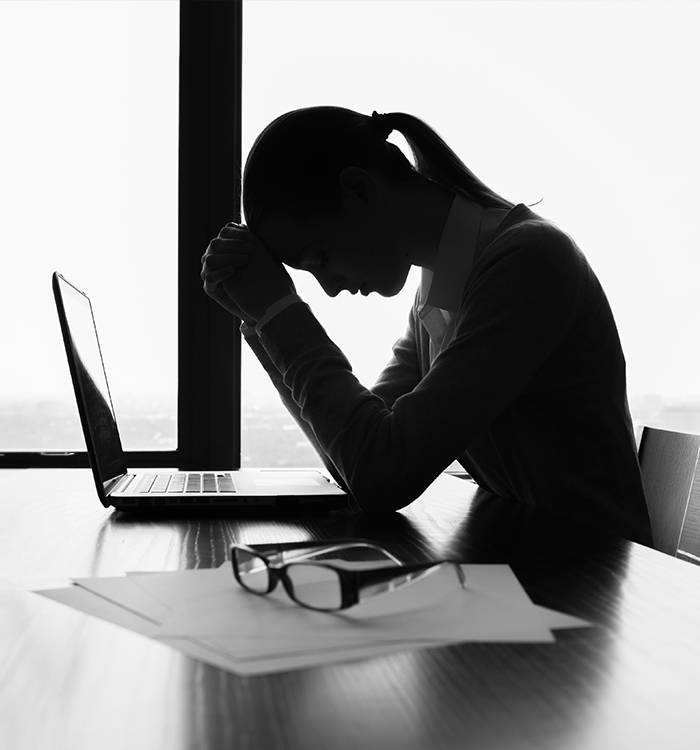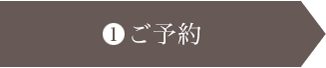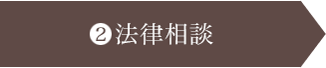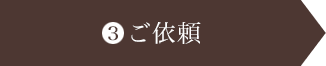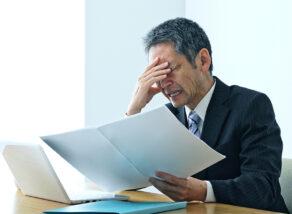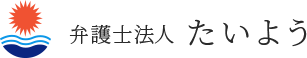労災保険からの補償を受けるには、原則として被災労働者又はその遺族が、被災労働者の勤務先事業所を管轄する労働基準監督署長に労災請求用紙等を提出する必要があります。そして、請求を受けた労働基準監督署長が支給もしくは不支給の決定を行います(不服申立制度もあります)。
補償を受けるための要件は以下のとおりです。
- 労働者であること
- 傷病等の結果が発生していること
- 業務上又は通勤による傷病等であること
- 各保険給付の種類に応じた支給要件を充たしていること
なお、労災保険は被災労働者の過失により労災事故が発生した場合でも利用できます。また、使用者に対する損害賠償請求では過失割合により賠償額が減額される過失相殺が問題になりますが、労災保険給付には過失相殺はありません。