企業の経営者にとって労務問題は避けては通れない問題のひとつです。特に最近の経済状況を反映し、リストラ・雇用調整という名のもとに多くの労働問題が発生しています。「雇用なき経済回復」といわれる労働者の雇用と労働条件を犠牲にする企業経営も見受けられます。「労務コンプライアンス」という言葉が良く使われるようになりましたが、労務を巡る多くの問題は法律によって厳しい規制があります。「従業員の処遇は会社の自由」というのはとんでもない勘違いです。「人材を活かす」ためにも労務問題への適切な対応は不可欠です。
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、解雇権を濫用したものとして無効とされます。
すなわち、解雇が有効とされるためには、解雇権の濫用とされないだけの正当な理由、合理的理由が必要なのです。
そこで、解雇する前には、当該事案が正当な理由があると認められる場合にあたるのかを十分に調査する場合があります。
まず、解雇の理由が正当なものである必要があります。設問のような事例でいえば、以下のように考えられます。
数週間の入院で病気自体が治療可能な場合には、解雇は原則認められないでしょう。
職場への復帰に予測できない程度の長期間を要するような場合には、労務提供が不能であるとして解雇しうると考えられます。
また、多くの就業規則には解雇事由として「病気により○○日間休業したとき」と定められている場合が多いと思いますが、その場合には定められた期間より短期間で解雇することは原則認められません。
なお、病気の従業員を解雇する際には、労働基準法による時期の制限にも留意してください。
ただ勤務態度や勤務状況が悪いだけでは解雇は認められず、解雇がやむを得ないと考えられる正当な理由が必要となります。
そこで、以下などの事情が必要となってくるものと考えられます。
・程度が甚だしいこと
・本人に帰責されるものであること
・解雇に至るまで個別の注意等の方策を尽くしたこと
重大な経歴詐称があった場合には解雇しうると考えられます。
もっとも、全ての場合に解雇できるわけではありません。具体的には、以下のような点を考慮します。
・就業規則に経歴詐称を解雇事由とする旨の有無
・経歴を詐称した態様
・意識的に詐称されたものであるか
・詐称された経歴の重要性の程度
・詐称部分と企業・詐称者が従事している業務内容との関連性
・使用者の提示していた求人条件に触れるものであるか
・使用者が労働契約締結前に真実の経歴を知っていれば採用していなかったと考えられるか
以上のような点からその経歴詐称行為が重大な信義則違反にあたる場合には解雇も許されるものと考えられます。
このような私生活上の行為の理由では容易に解雇は認められないと考えられます。
もっとも、この行為により会社の業務、会社の信用に著しい影響を及ぼした場合には解雇が認められることもあります。
また、当該理由自体は解雇理由として正当なものだとしても、その方法が慎重さを欠いている場合には、解雇権の濫用と判断されることもあります。
そこで、できる限り解雇以外の方法によって、解決しようとしたという経緯が必要です。
例えば、勤務態度の悪い従業員に対しては、いきなり懲戒解雇を行うというのではなく、まずは戒告・訓戒などの懲戒処分をおこない、それでも改善されない場合には諭旨解雇を試み、それも困難な場合に最終手段として懲戒解雇をおこなうというステップが重要です。
解雇につき正当な理由はなかったものと判断された場合、その解雇は無効となります。
つまり、被解雇者との雇用契約は解雇通告後もそのまま継続しているということになるのです。
そのため、被解雇者が会社に対し解雇の無効を主張して訴えた場合、解雇されなければ得られたであろう賃金を支払う義務が生じたり、被解雇者の職場復帰を命じられたりするおそれがあります。
場合によっては、突然1年分の賃金を一度に請求されるなどということにもなりかねません。
また、被解雇者には会社内に友人、知人がいる場合が多いでしょうから、会社内の雰囲気や士気も芳しくないものになるおそれがあります。
被解雇者が、会社に一方的に不当に解雇されたなどと声高に主張し、それが現在も働いている従業員の耳に入ることは、他の従業員が会社に対する不信感や嫌悪感を抱くきっかけとなるでしょう。
よって、従業員を解雇する際には極めて慎重に行わなければなりません。
正当な解雇事由があったとしても、当該従業員がその解雇事由の事実自体を争ったり、事実自体は認めてもこれによる解雇は不当だなどと主張したりした場合、その紛争解決に労力を費やさねばならないこととなります。
そこで、後々のトラブルを避けるため、まずは何より任意退職を実現する努力を行って下さい。
そのためには、解雇の理由を記載した「解雇理由書」を作成の上本人に呈示し、十分に話し合いを行うことが重要です。
本人が納得し、任意に退職することに合意した場合は、忘れずに退職届を提出してもらってください。
どれだけ説得しても当該従業員が退職しようとせず、解雇もやむを得ない場合、どのようなことに注意して解雇を行うべきでしょうか。
まず、被解雇者が解雇の不当性を争ってきた場合にも適法性を主張できる十分な証拠を残しておくべきです。
被解雇者は、解雇の理由となった事実が紛れもない事実だったとしても、それが客観的に証明できないことがわかっていればこれにつけこみ否認してくることがあり、このような場合には解決に長期間を要することになります。
解雇が正当であったことが明確に認められないということになると他の不当な目的により解雇したのではないかと疑われ、解雇権の濫用として無効と判断されてしまうおそれもあります。
例えば、勤務成績・欠勤日数など勤務状況が悪いことが何らかのデータで示すことが可能ならば、客観的な裏付け資料として残しておくべきでしょう。
また、被解雇者が問題ある行動を起こした場合、それを単なる口頭ではなく書面の形で注意して残しておくのがよいでしょう。
一度の問題行動で解雇したのではなく何度も注意を行うなどして解雇以外の解決方法を最大限模索したということが証明できれば、解雇がやむを得ないものであったと判断される一材料として会社に有利となります。
書面の記載も、最初は単に被解雇者の行動を指摘しこれに対し改善を促すような文面で構いませんが、2回目・3回目の注意の際にはこれでも改善されない場合には相応の処分を加えることを示唆するなどして指導・注意を加えるべきでしょう。
解雇の可能性もあることを指摘したにもかかわらず本人の態度に改善が見られなかったことは、解雇の正当性を判断する上で重要なひとつの事情となってくるものと考えられます。
なお、被解雇者が解雇理由となった自らの行動を認めている場合には、その旨一筆記載した覚書を作成しておけば、後々争われた場合にもそれが事実であったことを証明する一つの証拠となります。
後に紛争にならないようにするためには、適正な解雇手続を踏むことも重要です。
解雇は、使用者の一方的な意思によって労働契約を終了させる行為ですから、被解雇者に対する解雇通知によって解雇することができます。
もっとも、解雇しようとする場合には少なくとも30日前にその予告を行わなければなりません。
30日前に予告をしない場合には、30日以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
これは懲戒解雇の場合も同様であることに注意してください。
なお、解雇の意思表示は、法律上は文書によるものでも口頭によるものでも構わないとされていますが、通知の有無やその時期が争われたときのことを考え、文書によって通知しておくのがよいでしょう。
到達の有無が争われたときのことを考えれば、配達証明付郵便にて行うのがより望ましいです。
被解雇者が解雇無効を主張してきた場合、まずはどのような理由で解雇無効を主張しているのか確かめることが重要です。
解雇理由に争いがあるのか、解雇の際の手続的瑕疵を問題としているのか、また、どのような事実を主張しているのかによって、会社側が取るべき対処方法も変わってくるものです。
そこでまずは、どのような理由に基づいて解雇無効を主張しているのか明示することを求める書面を被解雇者に送るとよいでしょう。
これに対する被解雇者の反応によって、解雇無効の主張が単なる言いがかり的なものなのかを判断することもできます。
被解雇者の主張がはっきりしたら、弁護士に事情を説明しその後の対応を相談しましょう。
そのまま放置してしまうと、解雇無効の訴えが提訴されるおそれもあります。
また、不誠実な対応をした場合、そのような対応に基づく慰謝料まで請求されるおそれもあります。
迅速かつ適切に行動することが何より重要です。
事業者相談
新型コロナウィルスに関するご相談も承ります(初回無料)
創業5年目以内はスタートアップ支援(初回1時間まで無料)
※創業5年以内であることがわかる資料をご持参ください
事業者相談 11,000円~(税込)/ 60分
※追加30分ごとに5,500円(税込)
借金の相談 初回相談 無料
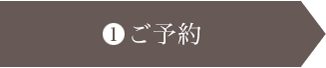 お電話または専用フォームよりご予約ください。
お電話または専用フォームよりご予約ください。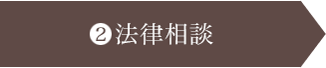 松山または大洲事務所にご来所ください。具体的な内容をおうかがいいたします。
松山または大洲事務所にご来所ください。具体的な内容をおうかがいいたします。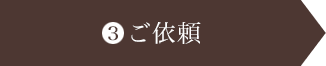 ご相談いただいた上で継続してサポートが必要かどうかをご判断ください。
ご相談いただいた上で継続してサポートが必要かどうかをご判断ください。新型コロナウィルスに関するご相談も
承ります(初回無料)
借金の相談 初回相談 無料
事業者相談
11,000円~(税込)/60分
※追加30分ごとに5,500円(税込)
 お電話または専用フォームよりご予約ください。
お電話または専用フォームよりご予約ください。 松山または大洲事務所にご来所ください。
松山または大洲事務所にご来所ください。 ご相談いただいた上で継続してサポートが
ご相談いただいた上で継続してサポートが