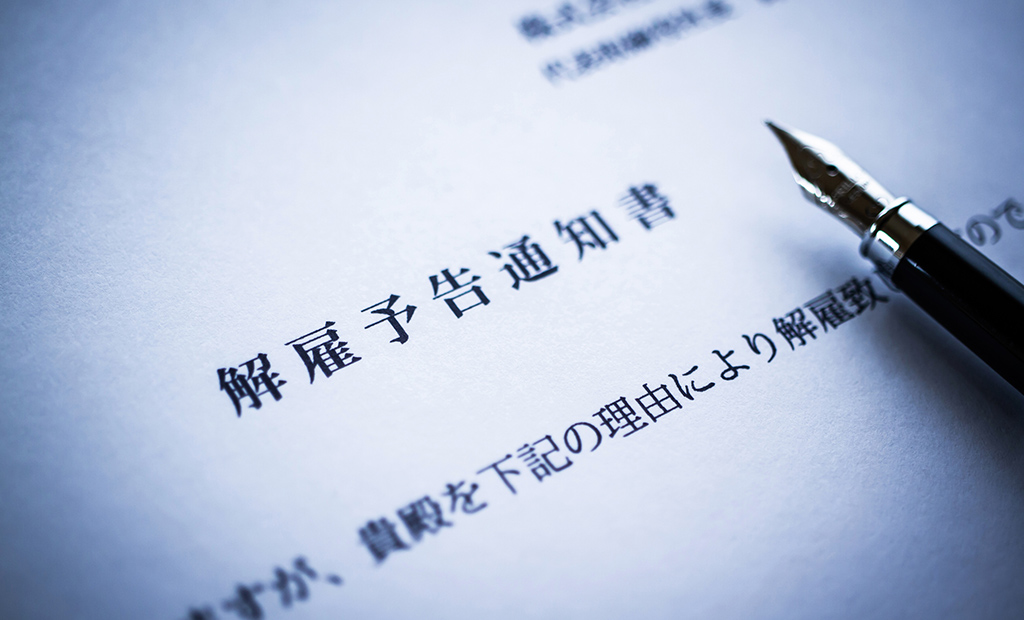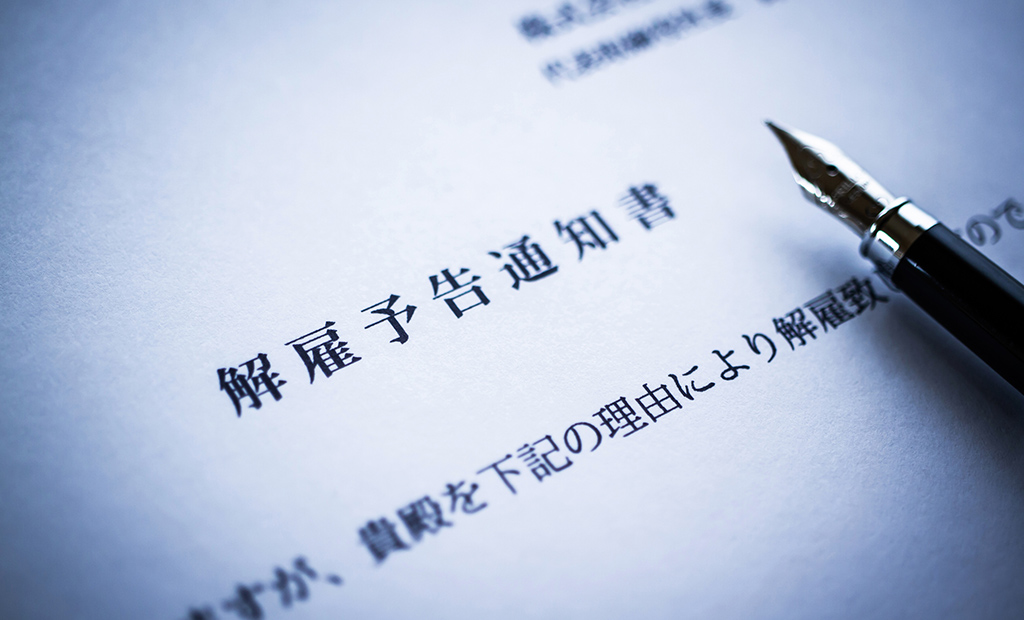
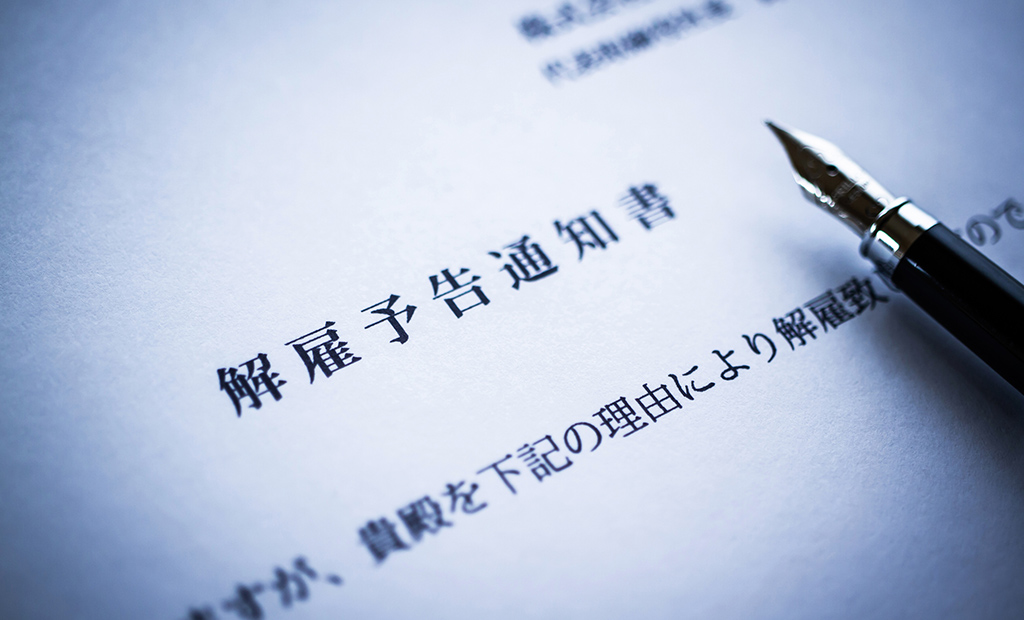
問題社員への対応は、職場秩序の維持と法的リスクの回避の両面から、慎重な検討が求められます。
本記事では、解雇の要件、手続き、判例を通じて、企業がとるべき適切な対応を解説します。
1 問題社員の解雇のハードルについて
企業内で問題行動を繰り返し、職場の秩序や他の社員に悪影響を及ぼす問題社員がいた場合、企業としては、その社員にすぐに辞めてもらいたいと考えるのが一般的です。
しかし、解雇は、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上相当と認められなければ、権利濫用として無効とされてしまいます。もし解雇が無効と判断された場合、解雇時から復職時までの未払賃金(いわゆる「バックペイ」)の支払い義務が発生するなど、企業には多大な経済的負担が生じる可能性があります。
2 退職勧奨の検討について
問題社員を解雇した場合、本人が解雇の有効性に納得せず、争いに発展する可能性があります。万一、解雇が無効とされた場合には、前述のとおりバックペイなどの経済的負担が発生します。
そのため、問題社員に退職してもらいたいと考える際には、まずは自主的な退職を促す「退職勧奨」を検討するべきです。円満な合意退職を目指すことで、企業にとってもリスクを回避しやすくなります。ただし、退職勧奨の方法が社員の自由意思を侵害するような場合には、違法と判断されることもありますので注意が必要です。
3 問題社員を解雇するうえでの注意点
- 就業規則や雇用契約書に定められた「解雇事由」に該当しているか確認する
- 客観的に合理的な理由があるか、社会通念上相当と判断されるかを検討する
- 解雇事由が重大かつ継続的で、改善の見込みがなく、他の手段がない場合に限り有効とされる
- 懲戒解雇が妥当か不明な場合は、より軽い懲戒処分(戒告・減給など)も検討する
4 解雇の種類について
解雇は、企業が一方的に雇用契約を終了させる手続きですが、その種類には「普通解雇」と「懲戒解雇」があります。
- 普通解雇:能力不足や協調性の欠如など、債務不履行を理由とした解雇
- 懲戒解雇:重大な企業秩序違反に対する制裁としての解雇
懲戒解雇は、対象社員が被る不利益が大きいため、普通解雇よりも厳しく有効性が審査されます。
やむを得ず解雇する場合には、まずは普通解雇の検討が基本です。
5 解雇手続のポイント
- 証拠の収集:メール、チャット、LINE、指導文書、録音データなどを確実に保存する
- 弁明の機会の付与:対象社員に対して、具体的な行為を説明し意見を聞く
- 解雇予告または予告手当:30日前の予告、または30日分以上の平均賃金を支払う
6 不当解雇と判断された事例
乙山商会事件
(大阪地裁平成25年6月21日)
石炭石油製品等の販売を目的とする会社に勤務する従業員が、会社に無断で業務関連情報 (取引に関する商品販売先の社名、担当者名、連絡先、交渉経過のメモ、受注数量、単価等の情報)を私物の記録媒体(ハードディスク)に保存をして、自宅に持ち帰りました。ハードディスクがなくなっていることに気付いた会社は、従業員が会社の機密情報が入ったハードディスクを自宅に持ち帰った行為が就業規則上の懲戒解雇事由に該当することを理由として、従業員を懲戒解雇しました。
判決では、ハードディスクに保存された情報が外部に流出したか否かは確認されておらず、ハードディスクの無断持ち帰りによって会社に何らかの具体的な損害が発生したと認められないことなどから、就業規則上の懲戒解雇事由に該当しないことを理由として、解雇が無効であると判断されました。
社会福祉法人蓬莱会事件
(東京高裁平成30年1月25日)
介護施設に勤務する介護職員が、すぐに否定的な意見を言い出し相手の話を聞かず話が前に進まない、引継ぎをする業務に困難が生じる、業務を正当な理由もなく一方的に断る、業務の追加・変更があるような場合に業務を拒否したり苦情を言い業務が円滑に稼働しないなどの問題行動を繰り返していました。
施設長は、職員を呼び出して指導をし、勤務態度を改めさせようとしましたが、職員は意に介しませんでした。そのため、施設長は、デイサービス部門への配置転換を打診しましたが(配置転換の勧告は業務命令として行われたものではありませんでした)、職員は配置転換に応じませんでした。そこで、最終的には解雇処分を下したという事例です。
高裁判決では、職員の問題行動を認定しつつも、職員を他の部署に配置転換したり他の上司の下で稼働させることを検討すべきであったにもかかわらず、施設長がデイサービス部門への配置転換を打診したにとどまり、これを超える解雇回避の措置を検討しなかったことなどを理由として、解雇が無効であると判断されました。
7 解雇が認められた事例
南淡漁業協同組合事件
(大阪高裁平成24年4月18日)
漁業協同組組合において信用業務(主に貯金業務)を担当していた職員が、職場で他の職員とほとんど言葉を交わさず、業務上必要な連絡もしないまま仕事を行うなど、必要なコミュニケーションをとらなくなりました。また、貯金名義人の承諾なしに貯金の振替をする、組合の指示に反して貯金払戻請求書を代筆する等の問題行動を独断で繰り返していました。
組合の代表者は職員に3回にわたって注意をしましたが、職員は勤務態度を改めようと全くしなかったため、勤務態度の改善が期待できないものと判断し、最終的には解雇処分を下したという事例です。
高裁判決では、職員の言動により様々な業務上の具体的な支障が生じており、代表者が3回にわたって注意をしたにもかかわらず職員が勤務態度を改めようと全くしなかったことなどを理由として、解雇が有効であると判断されました。
KDDI事件
(東京高裁平成30年11月8日)
従業員が、3年以上の期間にわたり、就業規則、賃金規定、社宅規程、単身赴任基準、国内旅費規程の要件に該当しないにもかかわらず、単身赴任手当等を受給したり、借上げ社宅に適正な賃料を負担しないで居住していました。
高裁判決では、従業員が積極的に虚偽の事実を申告して各種手当を不正に受給したり本来支払うべき債務の支払を不正に免れたりするなど、雇用関係を継続する前提となる信頼関係を回復困難なほどに毀損する背信行為を複数回にわたり行い、会社に400万円を超える損害を生じさせたこと、懲戒解雇がされるまで明確な謝罪や被害弁償を行うこともなかったことなどを理由として、解雇が有効であると判断されました。
8 弁護士によるサポート
問題社員への対応を怠れば、職場環境の悪化や企業の信用低下を招く恐れがあります。
一方で、対応を誤れば企業が法的責任を問われる可能性もあります。
弁護士法人たいようでは、企業の立場に立った問題社員対応を多数サポートしており、
退職勧奨から解雇手続まで、実務に即した対応策をご提案いたします。
問題社員対応にお困りの際は、ぜひご相談ください。


1 モンスター社員(問題社員)とは?
「モンスター社員」とは、企業内で問題行動を繰り返し、職場の秩序や他の社員に悪影響を及ぼす社員を指します。具体的には、業務命令に従わない、同僚や上司への暴言・暴力、ハラスメント行為、無断欠勤・遅刻の常習、組織を混乱させる行動をとるなど、職場環境や企業の運営に支障をきたす行為を行う社員です。
モンスター社員の存在は、企業の生産性や職場環境の悪化を招くだけでなく、法的なトラブルを引き起こすリスクも高まります。そのため、企業は早期に問題を認識し、適切な対応を講じることが求められます。
2 モンスター社員・問題社員の種類
モンスター社員(問題社員)には、様々な種類が存在します。
- ハラスメント型:パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントなど、様々なハラスメント行為を行う従業員。
- 怠慢・無責任型:業務を怠慢したり、責任を放棄したりする従業員。
- 攻撃型:同僚や上司に対して攻撃的な言動を行う従業員。
- 依存型:過度に会社や上司に依存し、自律的に業務を遂行できない従業員。
- 自己中心的型:自己中心的で、周囲への配慮に欠ける従業員。
- 経歴詐称・不正型:経歴詐称や不正行為を行う従業員。
3 モンスター社員を放置するリスク
モンスター社員(問題社員)を放置すると、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
- 企業イメージの悪化:モンスター社員の行動がSNS等で拡散されると、企業イメージが著しく悪化する可能性があります。
- 訴訟リスク:ハラスメント行為や不当解雇など、モンスター社員に関連する訴訟リスクが高まります。
- 他の従業員のモチベーション低下:モンスター社員の存在は、他の従業員のモチベーションを低下させ、離職率を高める可能性があります。
- 業績悪化:モンスター社員の行動は、企業の業績に悪影響を与える可能性があります。
4 モンスター社員を
辞めさせることはできるのか?
モンスター社員(問題社員)を辞めさせることは、法的には可能ですが、慎重な対応が必要です。
1 退職勧奨
退職勧奨は、従業員に自主的な退職を促す方法です。退職勧奨を行う際は、強要にならないよう注意が必要です。
2 合意退職
会社と従業員が合意の上で退職する方法です。合意退職を行う際は、合意内容を書面に残しておくことが重要です。
3 解雇
解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である場合にのみ有効となります。
モンスター社員の行動が解雇理由に該当するかどうかは、個別のケースによって判断されます
5 ケース別のモンスター社員対応
モンスター社員(問題社員)への対応は、その種類や状況によって異なります。
1 ハラスメント型
事実確認を徹底し、就業規則に基づいた処分を行う必要があります。
2 怠慢・無責任型
業務改善を促し、改善が見られない場合は処分を検討する必要があります。
3 攻撃型
事実確認を徹底し、必要に応じて配置転換や就業規則に基づいた処分を検討する必要があります。
4 依存型
自律的な業務遂行を促し、必要に応じて専門家の支援を検討する必要があります。
5 自己中心的型
周囲への配慮を促し、改善が見られない場合は必要に応じて配置転換や就業規則に基づいた処分を検討する必要があります。
6 経歴詐称・不正型
事実確認を徹底し、懲戒解雇を含めた厳正な処分を行う必要があります。
6 モンスター社員対応について
弁護士に依頼する際の費用相場
弁護士に依頼する際の費用相場は、以下の通りです。
- 相談料:30分5,000円~1万円程度
- 交渉・代理業務:着手金20万円~50万円、成功報酬10%~20%
費用は事案の難易度や弁護士事務所によって異なります。事前に見積もりを確認することをお勧めします。
7 モンスター社員対応を
実施する際の注意点
- 証拠を残す:業務命令違反やハラスメント行為の証拠を、メールやメモ、録音などで確保します。
- 就業規則の整備:懲戒処分や解雇に関する規定を明確にし、社員に周知徹底しておきます。
- 弁護士への相談:対応が難しい場合は、早期に専門家に相談することが重要です。
8 弁護士によるモンスター社員対応
弁護士は、モンスター社員対応において、以下のサポートを行います。
- 法的アドバイス:企業が法令を遵守した対応を取れるよう支援。
- 交渉や調停の代理:社員とのトラブル解決をサポート。
- 解雇手続きの適切な実施:トラブルを未然に防ぐための支援。
- 就業規則の見直し:モンスター社員対策として、就業規則の見直しをサポートします。
9 モンスター社員対応に関する
弁護士法人たいようの解決実績
弁護士法人たいようでは、過去に多くのモンスター社員対応を成功に導いています。
具体例として、パワハラ社員の早期退職の実現や、訴訟を回避した円満解決などがあります。
10 モンスター社員対応
(問題社員対応)については
弁護士にご相談ください
モンスター社員への対応は、企業のリスクマネジメントにおいて非常に重要です。
困難なケースでも、専門家のサポートがあれば適切な対応が可能です。
弁護士法人たいようでは、企業の状況に合わせた最適な解決策を提供いたしますので、ぜひご相談ください。


企業の人事担当者や経営者にとって、従業員のパフォーマンス管理は重要な課題です。
特に、「ローパフォーマー社員」や「問題社員」と呼ばれる従業員への対応は、慎重さを要します。本記事では、これらの用語の定義、特徴、企業が取るべき対応、法的注意点、放置のリスク、関連判例について解説します。
1 ローパフォーマー社員とは?
ローパフォーマー社員とは、一般的に、企業が期待する成果や能力水準に達していない従業員を指します。
これは法律用語ではなく、企業によって定義や基準は異なります。重要なのは、客観的な指標(数値目標、人事評価など)に基づいて評価することです。
2 問題社員とは?
一方、問題社員とは、能力不足だけでなく、勤務態度、協調性、規律意識などに問題があり、企業秩序を乱す可能性のある従業員を指します。
ローパフォーマー社員も問題社員の一部と捉えることができますが、問題社員はより広範な概念です。
- ローパフォーマー社員:営業成績が常に目標未達、納期遅延が多い、ミスが多いなど。
- 問題社員:無断欠勤、遅刻が多い、ハラスメント行為を行う、業務指示に従わないなど。
3 ローパフォーマー社員の特徴
ローパフォーマー社員には、以下のような特徴が見られることがあります。
- 能力不足:業務に必要な知識、スキル、経験が不足している。
- 意欲の欠如:仕事に対するモチベーションが低い、指示待ちの姿勢。
- コミュニケーション不足:報連相ができない、周囲との連携が取れない。
- 自己認識のずれ:自分の能力や成果を過大評価している。
- 責任感の欠如:自分の仕事に対する責任感が薄い。
4 ローパフォーマー社員が生まれる理由
ローパフォーマー社員が生まれる原因は様々ですが、以下のような要因が考えられます。
- 採用ミスマッチ:企業の求める能力や適性と、従業員の能力・適性が合っていない。
- 教育・指導不足:適切な研修やOJT(On-the-Job Training)が行われていない。
- 評価制度の不備:評価基準が曖昧、フィードバックが不十分。
- 職場環境の問題:ハラスメント、人間関係の悪化、過重労働など。
- 従業員個人の問題:家庭の事情、健康問題、個人的な悩みなど。
5 ローパフォーマー社員を
放置するリスク
ローパフォーマー社員を放置すると、以下のようなリスクが生じます。
- 生産性の低下:企業全体の業績に悪影響を及ぼします。
- 周囲の士気低下:他の従業員のモチベーションが低下します。
- 企業風土の悪化:問題社員を放置することで、企業全体の規律が緩みます。
以上のようなリスクを回避するため、ローパフォーマー社員に対しては会社として適切に対応していくことが求められます。
6 ローパフォーマー社員の解雇を
検討する前に企業が行うべきこと
ローパフォーマー社員に対して、いきなり解雇を検討するのは避けるべきです。
日本の労働法では、解雇は厳しく制限されており、安易に解雇を行うことは不当解雇と判断されるリスクがあります。
まずは、以下のステップを踏み、本人のパフォーマンスに改善の余地がないか、会社として解雇を回避するための努力を行うことが重要です。
1 問題点の明確化と本人へのフィードバック
- 客観的なデータに基づき、問題点を具体的に特定し、本人に伝えます。
- 改善目標と期限を設定し、書面で共有します。
2 指導・教育の実施
- 本人の能力や適性に応じた指導・教育を行います。
- 研修、OJT、メンター制度などを活用します。
3 配置転換の検討
- 指導・教育でも改善が見られない場合、本人の適性に合った部署への配置転換を検討します。
4 改善状況のモニタリングと再評価
- 定期的に面談を行い、改善状況を確認し、評価します。
7 ローパフォーマー社員を解雇する際の注意点
上記の手順を踏んでも改善が見られないような場合には、やむを得ず解雇を検討する必要があります。
この場合、以下の点に注意が必要です。
- 解雇の正当な理由:「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要です(労働契約法16条)。
能力不足を理由とする解雇は、特に慎重な判断が必要です。
- 解雇予告:原則として30日前の予告か、30日分以上の解雇予告手当が必要です(労働基準法20条)。
- 就業規則の確認:解雇に関する規定を確認し、手続きを遵守します。
- 証拠の確保:解雇の正当性を裏付ける証拠(人事評価記録、指導記録、面談記録など)を収集・保管します。
8 まとめ
ローパフォーマー社員や問題社員への対応は、企業にとって重要な課題です。
法的リスクを回避しつつ、適切な対応を行うためには、弁護士などの専門家への相談も検討しながら、慎重に進めることが求められます。