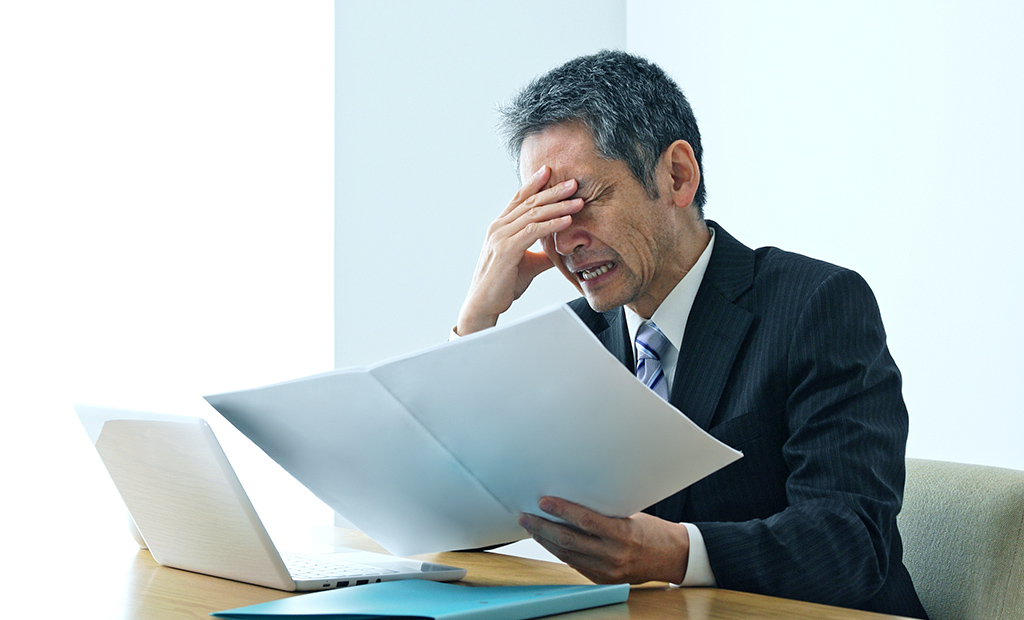職場における「問題社員」への対応は、経営者や人事担当者の大きな悩みの一つではないでしょうか。勤務態度が悪い、指示に従わない、遅刻や無断欠勤を繰り返すなど、職場秩序に悪影響を及ぼす社員への適切な対応は、企業の健全な運営にとって非常に重要です。
しかし、感情に任せた対応や、法律的に不適切な指導を行ってしまうと、逆に会社側が不利な立場に立たされることもあります。そこで今回は、弁護士の視点から、問題社員への指導方法や注意点について、わかりやすく解説します。
1 問題社員への指導とは?
「問題社員」とは、就業規則や職場のルールを守らなかったり、業務遂行に著しく問題があったりする社員を指します。ただし、単に上司や同僚と性格が合わない、やや不器用といった理由だけでは「問題社員」とは言えません。
指導の目的は、あくまで「改善」を促すことです。企業は、社員に対して指導や教育の機会を提供する義務があります。いきなり懲戒処分や解雇に踏み切るのではなく、まずは適切な手順を踏んで指導を行うことが重要です。
2 問題社員への具体的な指導方法とは?
指導は段階を踏んで行うのが基本です。一般的には、以下のような流れが考えられます。
- 口頭での注意
- 書面での注意・指導
- 面談記録の作成
- 懲戒処分(軽度→重度)
- 最終的に必要であれば解雇
いずれの段階でも、「記録を残す」ことが非常に重要です。後からトラブルになった際に、会社側が正当な対応をしたことを証明するための重要な証拠になります。
3 「口頭注意」の注意点について
軽微な問題行動については、まず口頭で注意することが一般的です。ただし、この段階でも「誰が」「いつ」「どのような内容で」注意をしたかを、メモなどで記録しておくことをおすすめします。
また、注意の際には感情的にならず、冷静に事実を伝えることが大切です。「あなたはダメだ」といった人格否定ではなく、「○日の会議に遅刻しました。今後は時間を守ってください」と具体的な事実と改善点を伝えましょう。
4 注意指導を書面で行う方法について
問題行動が改善されない場合は、書面での指導に移行します。書面による注意は、後に証拠として活用できる点で非常に有効です。注意文書には、以下のような内容を含めます。
- 行動の具体的内容(何が問題だったか)
- 会社のルールとの関係(就業規則違反等)
- 今後の期待・指導内容
- 再発時の対応方針(懲戒の可能性など)
本人に内容を説明し、可能であれば署名・捺印をもらいましょう。
5 問題社員対応は事前の準備がポイント
問題社員の対応は個別に判断する必要がありますが、対応の流れや記録の形式がバラバラだと、対応に一貫性がなくなり、会社の信用も損なわれかねません。そこで、社内で使用する「指導書式」や「対応マニュアル」をあらかじめ整備しておくことが有効です。
弁護士が監修した対応パッケージを導入することなどで、指導の精度が高まり、リスクを最小限に抑えることができます。
6 問題社員を指導しても
改善されない場合
注意や指導を繰り返しても改善が見られない場合、最終的には懲戒処分や解雇も選択肢となります。ただし、日本の労働法では「解雇は最後の手段」とされており、かなりハードルが高く、十分な指導・改善の機会を与えた上でなければ、解雇は無効とされる可能性があります。
特に「普通解雇」や「懲戒解雇」を行う際には、就業規則に定められた手続きを丁寧に踏む必要があり、慎重な判断が求められます。
7 弁護士による問題社員対応
問題社員対応には、法的な知識と豊富な実務経験が不可欠です。弁護士に相談することで、指導の流れや記録方法、適切な表現の仕方などについて専門的なアドバイスが受けられます。
また、状況に応じた懲戒手続きの進め方や、万が一トラブルになった場合の対応策についても、法的観点からバックアップが可能です。
8 まずは弁護士にご相談ください
問題社員への対応は、放置しても、強硬に出ても、会社にとってリスクとなることがあります。だからこそ、早い段階で専門家のアドバイスを受けることが重要です。仮に対応を間違うと、外部ユニオンから団体交渉を求められたりする場合などもあります。
当事務所では、企業の皆様の健全な労務管理を支援するため、問題社員対応のご相談を多数お受けしています。初回相談から具体的な対応プランのご提案まで、しっかりとサポートいたします。
「こんなことで相談してもいいのかな?」と思われることでも、ぜひ一度ご相談ください。あなたの会社のリスクを減らす第一歩になります。